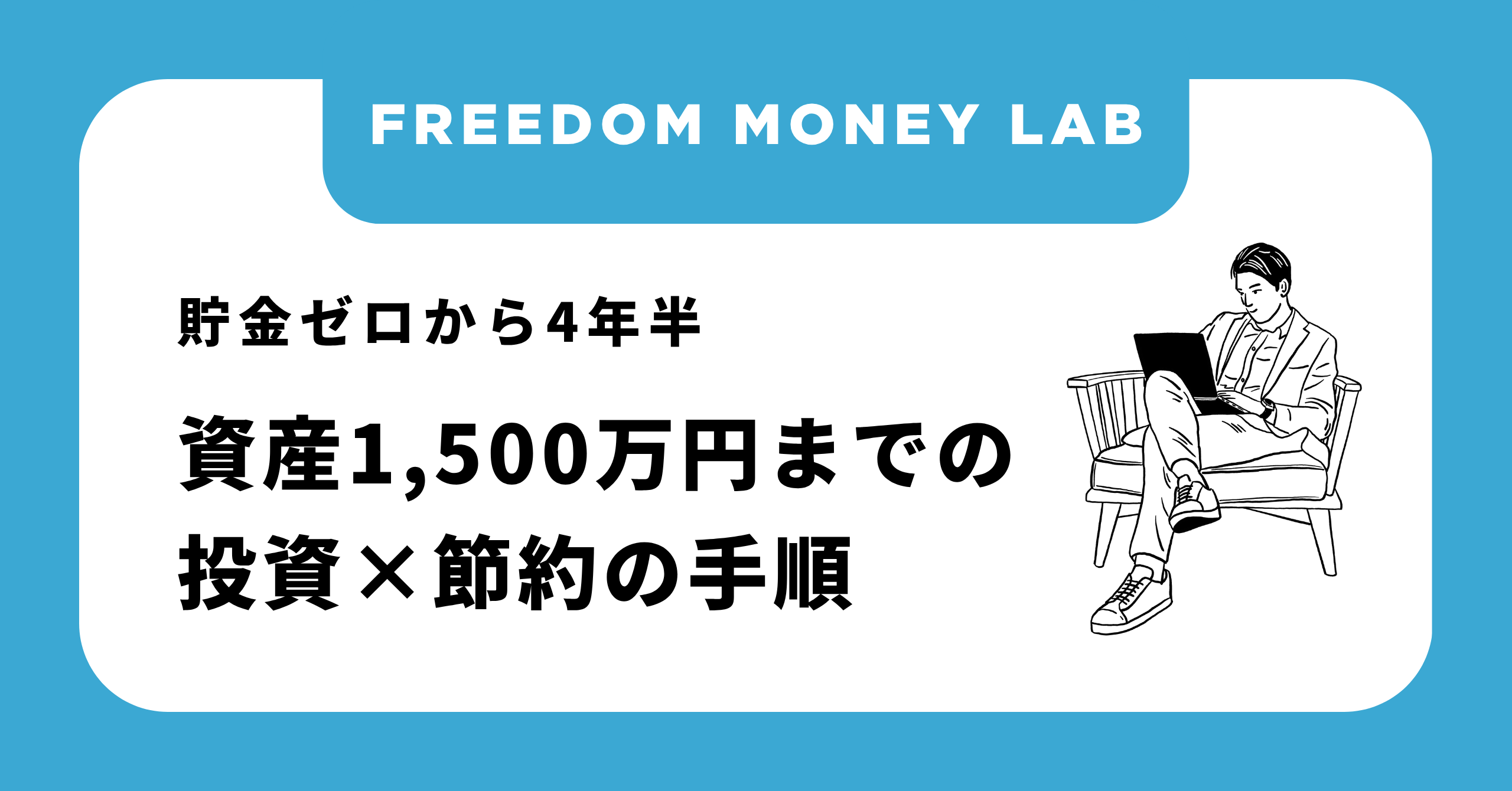- はじめに|貯金ゼロからスタートしたリアルな資産形成の記録
- 資産形成を始めたきっかけ
- 年ごとの資産推移と取り組み内容
- まとめ|資産形成で大切なのは最初の2年間
- 次回予告|コア・サテライト戦略について
はじめに|貯金ゼロからスタートしたリアルな資産形成の記録
28歳まで貯金ゼロ。
どこにでもいる普通の会社員だった私が、
わずか4年半で資産1,500万円を築きました。
特別な収入があったわけでも、運よく一発当てたわけでもありません。
正しい知識を学び、支出を整え、シンプルな投資を継続してきただけです。
この記事では、年ごとの資産推移とともに、リアルな実践内容を詳しく紹介します。
これから資産形成を始めたい方の参考になれば幸いです。
資産形成を始めたきっかけ
資産形成に本気で取り組み始めたのは、2021年5月のことでした。
実はそれよりも4年前、25歳の頃から「将来のお金のことを考えなきゃ」とは思っていました。
でも、なんとなく先延ばしにして、実際には何も始められないまま4年が経過していました。
「もしあのとき始めていれば…」という後悔が今でもあります。
25歳から始めていれば、FIRE(早期リタイア)も現実的だったかもしれません。
だからこそ、今こうして発信をしています。
資産形成は、1日でも早く始めることが何よりのアドバンテージになると、
実感しているからです。
特に、収入がなかなか増えない一方で、物価や税金の負担は増えている今の時代。
何もしないままでいるリスクの方が、ずっと大きいと感じています。
年ごとの資産推移と取り組み内容
ここからは、私がどのように資産を増やしてきたのか、
年ごとの資産推移を見ながら詳しく紹介していきます。
【1年目】資産0円 → 200万円(2021年〜2022年:支出を見直した1年)
この年は、とにかく「支出の見直し」と「徹底的な節約」に取り組みました。
スマホは格安SIMに変更し、サブスクもAmazon会員以外はすべて解約。
外食は一切やめて完全に自炊生活。コンビニでの飲み物やちょっとした買い物も
全カットしました。
その結果、毎月の黒字額は約15万円。
手取り22万円のうち、7割近くを貯蓄と投資に回すことができました。
投資は、つみたてNISAと特定口座を活用し、S&P500やオルカン
NASDAQ100といった王道のインデックスファンドを中心にスタート。
ただ、当時はまだ知識が浅かったこともあり、
iFreeレバナスや楽天レバナスといったレバレッジ型の投資信託にも
手を出していました。
正直に言うと、これはまったくおすすめしません。
理由はシンプルです。
- 下落相場での含み損がエグい
- 売却までに3〜4日かかる(日本の投信の仕様)
- キャピタルゲイン狙いなら米国個別株の方が動きやすい
実際、4年間運用して比較した結果、レバナスよりも
S&P500やNASDAQ100を積み立てていた方が安定してリターンを得られました。
もし「短期で勝負したい」と思うなら、正直レバナスよりも
米国の個別株で勝負する方が圧倒的に勝てると、経験を通じて実感しています。
この1年間、運用益としてはほぼトントン。
レバナスではやや含み損、S&P500ではわずかに
含み益といった状況でしたが、何よりも大きかったのは、
「貯金ゼロだった自分が、1年間で200万円貯金できた。」
という事実です。
1年間で200万円を貯めたという実績が、以降の資産形成において大きな自信となりました。
【2年目】資産200万円 → 420万円(2022年〜2023年:下落相場で忍耐を学んだ1年)
この年は、市場環境が非常に厳しかった1年でした。
S&P500は年間で約19.5%の下落を記録し、株式市場全体が冷え込んでいました。
投資を始めて間もない私にとって、正直なところかなり大きなショックでした。
しかし実際には、資産は思ったほど減っていませんでした。
理由は為替です。2022年は、1ドル=115円前後から
年末には131円付近まで円安が進行。ドル建てでは下落しても、
円換算では目減りが緩和され、円ベースの資産は約8%減にとどまりました。
この経験を通して、「外貨資産を持つ意味」や「為替リスクの大きさ」を
初めて肌で実感できました。
また、少額ではありますがFXにも取り組んでいたことで、
金利と通貨の関係についての理解を深めることができました。
さらに、2022年の後半には日本株への投資もスタート。
2023年に入ると徐々に市場が回復し、6月には資産が500万円を突破しました。
投資2年目は「投資/節約の継続の難しさ」を学んだ年でした。
正直、2022年がいちばんモチベを保つのが難しかった。
継続してコツコツ積立投資しても結果が出ない。
でも今振り返ると——
下落相場で市場が絶望に包まれてる時が株の仕込み時。
この時にコツコツ続けていた投資がのちに大きなリターンとなって
現在の資産形成を押し上げる原動力になりました。
【3年目】資産420万円 → 770万円(2023年〜2024年:AIブームの追い風を感じた年)
2022年の絶望の株式相場から一転、2023年はこれまでと違う年になりました。
この年は相場が回復傾向にあり、やっとコツコツ投資してた資産がプラ転して
大きくプラスになりました。
市場を押し上げた大きな成長ドライバーがAIの登場です。
ChatGPTが2022年末にサービスを開始し、
現実のプロダクトとして広がったことで、空気が一変した感がありました。
そして投資資金が500万円を超えたあたりから、
相場の動きによるリターンをはっきり実感できるようになりました。
さらに2024年1月からは新NISAが始まり、非課税枠の拡大も追い風に。
投資を続けるうえで、より有利な環境が整ったと感じました。
ただし生活スタイルは変えず、月15万円の積立投資を継続。
支出を抑える習慣は、1年目から今もずっと続けています。
資産が目に見えて増えるにつれ、モチベーションも自然と高まりました。
「このまま続けていけば、本当に自由になれる」
と確信できた1年だったと思います。
【4年目】資産770万円 → 1,075万円(2024年〜2025年:淡々と継続し、自信が芽生えた年)
この年も、これまでと同じく「淡々と継続」がテーマでした。
「トランプショック」と呼ばれる急落局面でも、焦らずに割安となったAI関連株を買い増し。
新NISAを活用しながら、S&P500・全世界株・米国個別株を
コツコツと積み上げていきました。
不安定な相場の中でもブレずに続けられたことが、
自分の中で「投資に対する軸」や「自信」を一段引き上げてくれた一年だったと感じます。
資産1000万円を突破(2024年11月)
スタートから約3年半(40ヶ月)。
ついに、資産は1,000万円を突破しました。
1000万円を超えて感じた3つの変化
① 「1/2の分身」が働く感覚
お金が自分の代わりに働いてくれている――。
資産が利益を生み、複利で増えていく実感がありました。
「これが不労所得か」と感じた瞬間です。
② 安心感と自信の高まり
1,000万円という数字が与える安心感は想像以上でした。
「何かあっても大丈夫」という余裕と、「ここまで積み上げてきた」という自信。
この2つが、精神的な安定につながりました。
③ “死ぬ気で節約”から“自分への投資”へ
それまでは生活費を削ることに全力を注いでいましたが、
1,000万円を超えてからは「どうお金を使えば将来の自分が成長できるか」
を考えるようになりました。
自己投資の具体例
- 中古の M1 Max MacBook を導入
- 長年使っていた iPhone 8 を中古の iPhone 12 に買い替え
- Web制作のオンライン講座 を受講
- AIツールのサブスク を契約
どれも贅沢ではなく、未来の自分の生産性や知識を高めるための投資。
「我慢ではなく、選択する節約」を意識するようになりました。
FIREが見え始めた時期
1000万円を突破した直後は「減らしたくない」という気持ちが強く、
支出をかなり抑えていました。
しかし、資産が1,200万円を超えた頃からは、
「このままいけば数年でFIREできるな」と思うようになりました。
そして同時に――
「このままの自分ではダメだ」
と感じ、FIRE(経済的自立)に向けての行動を始めました。
この頃から、お金のために働く人生から、好きなことで生きる人生へ
少しずつシフトし始めた感覚があります。
価値の高いものにお金を使う思考
1000万円を築く過程で身についたのは、
「高い価値を安く手に入れる」という感覚でした。
これは、株を仕込むときも同じです。
過小評価されていて、成長性が期待できる銘柄を買えば、
リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
お金の使い方もまったく同じ。ブランド品を買うよりも、
本当に必要で、長く使えるもの――そして自分を成長させてくれるものに投資する。
この思考が、今の僕の行動の軸になっています。
この時期に気をつけたいこと
ちなみに、この1000万円前後の段階では、大きな出費は避けたほうが良いと思います。
たとえば、新しい家や車を買ってしまうと、またやり直しです。
やっと“投資で大きなリターンを狙える元本”を手にしているのに、
ここで減らしてしまうのは、あまりにももったいない。
この時期こそ、「お金を守りながら増やす」フェーズだと感じました。
【5年目】資産1,075万円 → 1,550万円(2025年〜:AI相場の回復で一気に資産が伸びた年)
5年目に関しては、まだ1年の途中ですが、
わずか半年で資産が約420万円増えています。
やっていることは、4年前から何も変わっていません。
毎月15万円の余剰資金をつくり、
その15万円を淡々と投資に回す——この“絶対ルール”を守り続けているだけです。
トランプ相場からの回復とAI銘柄の上昇
資産の伸び方が変わった最大の要因は、
あのトランプショックの真っ只中で仕込んだAI銘柄たちが、
その後の回復相場で一気に花開いたことです。
あの混乱の中で、AI関連株を中心に買い増しました。
具体的には、
- Sofi(ソーファイ・テクノロジー)
- AppLovin(アップラビン)
- Micron(マイクロン・テクノロジー)
この3銘柄を中心にポジションを増やしました。
今振り返ると、
「怖いけど買えた」あのタイミングが大きな分岐点でした。
現在では、これらすべてが2倍以上の含み益になっています。
さらに、すでに保有していたNVIDIAやPalantirといった銘柄も
順調に利益を伸ばし、資産全体を押し上げる結果となりました。
勝負はどこで買うかで決まる
含み益について言えば、2倍まで乗せられた時点でほぼ安泰。
そこまで来ると、あとは“高みの見物”に近い感覚になります。
つまり、勝負は「どこで買うか」に尽きる。
個別株は買うタイミングを間違えると普通に負けます。
逆に、いいポイントで仕込んで含み益が+50%を超えてくるとメンタルが一気に楽になる。
含み益が減ってきたら買い増しのチャンス、
増えているなら見守って放置。このサイクルに入れば相場に振り回されません。
まだ言語化の途中だけど、体感としては――
「良い位置で買う」→「+50%で気持ちが軽くなる」→「+100%(2倍)で余裕ゾーン」。
実際、Palantirは約8倍まで伸びた。
もし最初の30万円をそのまま握っていれば、含み益だけで240万円。
やっぱり個別株投資は、仕込むタイミングがすべて。
これは、投資信託の積立とはまったく違う戦略です。
まとめ|資産形成で大切なのは最初の2年間
振り返ってみて、一番大きかったのは最初の2年間です。
この2年間で、貯金ゼロの自分が400万円を作れたこと。
この経験が、その後の投資の土台になりました。
資産形成って、最初の助走が一番しんどいんですよ。
でも、逆に言えば——
最初の2年を乗り切れたら、あとは“流れに乗るだけ
そして、その2年間を乗り切ったら資産1000万円はすぐです。
なのでこれから資産形成を始める人に伝えたいのは――
投資している前提で、
貯金ゼロから400万円まで行けたら、1000万円という山の半分は登り切っている。
ということです。
そこを越えたあたりから、複利の力で増えていくようになります。
続けた人だけが見える景色
S&P500や全世界株にコツコツ積み立て、
下落局面では恐れず買い増す。
それを続けるだけで、1000万円は現実的な数字になります。
目安としては、
- 月10万円の積立で約5年
- 月5万円なら約8年
- 月3万円でも約10年
焦らず、地道に。やってみれば分かりますが、複利の力は想像以上です。
下落相場こそ、成長のチャンス
正直、投資を始めた頃は「年利10%なんて出るのか?」と思ってました。
でも、実際に経験して分かったのは、
リターンは“我慢の時期”を越えた先にやってくるということ。
特に、株価が下がっている時に買えた銘柄が、後に大きく資産を押し上げてくれました。
最後に
4年半で1,550万円。この数字には満足していますが、まだ通過点です。
「もっと攻めていれば2,000万円もいけた」
そんな悔しさもあります。
実際、Palantirは8倍、NVIDIAも仕込みチャンスがありました。
でも、それも含めて、“自分の軌跡”として誇れる5年間です。
次回予告|コア・サテライト戦略について
この記事の中で、
PalantirやNVIDIAといった銘柄に少額ながら投資していたことをお話ししました。
正直、「もっと大きくベットできていれば…」という後悔は、今でも少し残っています。
なぜ、当時そこまで踏み切れなかったのか?
それは、自分の中で投資判断の基準——つまり「コア・サテライト戦略」への理解が
曖昧だったからだと、今では思っています。
次回は、私が現在も実践している
「コア・サテライト投資法」について、詳しく解説します。
この戦略は、
- リスクを抑えながら
- 成長のチャンスを狙え
- 再現性が高い
という特長があり、今では自信を持って投資判断できる軸となっています。
正直、あまり人に教えたくない内容ではありますが、
ですが、この記事をここまで読んでくださった方には、特別にお伝えするつもりです。
投資判断に迷っている方や、これから本格的に資産形成を始めたい方には、
必ず参考になるはずです。
ぜひ次回の記事もお楽しみに。